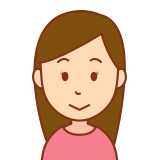
- ワークライフバランスとは一体なんなの?
- ワークライフバランスが実現することで、どんなメリットがあるの?
最近さまざまなメディア等で、耳にすることが多くなった”ワークライフバランス”ですが、実際に私たちの生活にどのような影響を及ぼしているのか、気になっているのではないでしょうか。
“ワークライフバランス”とは、いわば「生活と仕事の調和を図りましょう」という一つの理念を指します。
日本では政府を中心とした”働き方改革”が年々進んできていますが、働き方に多様性が生まれることで、より生活の質や仕事へのモチベーションが向上したり、といったプラスの影響が生まれている訳です。
少し前の日本社会では誰よりも長く一生懸命働くことが美徳とされていましたが、今は成果主義に切り替わったことで、長時間労働も見直されてきています。
この記事ではワークライフバランスに関する考え方や実現した際のメリット、その他、企業側の主な取り組み等に関してわかりやすく解説しています。
最後まで読んでいただくことで、ワークライフバランスに対して、正しい知識を身につけることができるでしょう。
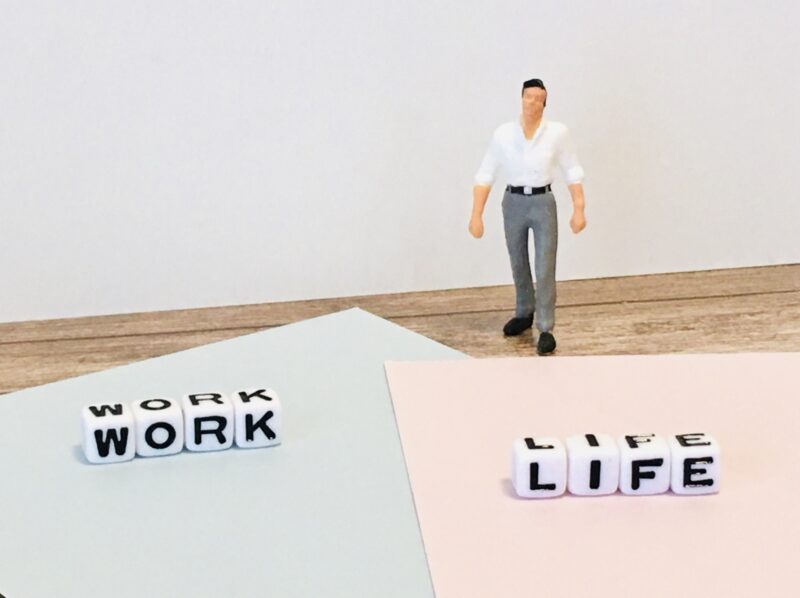
ワークライフバランスとは生活と仕事の調和のこと
ワークライフバランスとは、生活と仕事の調和と調整を意味します。
解釈自体は人によってさまざまではありますが、簡単にいったら生活と仕事を別々に考えずに、相関関係で考えて取り組むということです。
- 生活が充実する
- 仕事にもプラスの影響が出る
- 仕事が充実すると生活もより良くなる
今まではプライベートと仕事は別々に考えて、行動するのが当たり前とされてきました。
しかし、ワークライフバランスの考え方は、生活と仕事を一緒に考えて人生の充実度を上げる、という狙いがあります。
ワークライフバランスの定義
内閣府のサイトによるとワークライフバランスの定義は、以下のように定めてあります。
国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、
子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会。
出典:「仕事と生活の調和」推進サイト
仕事は人生の大半の時間を占めている訳ですが、人生が仕事だけだと家庭が疎かになり、子育てや子づくりに励むことができません。
そのため、ワークライフバランスの考え方を浸透させ、仕事だけではなく生活の充実を図り、生き方や働き方に多様性を持たせようという訳です。
また、人生100年時代といわれる中で、一つの働き方だけでは限界があるため、各年代に合わせた生き方や働き方に変化させる必要があります。
ワークライフバランスの歴史
ワークライフバランスの概念は、1980年代後半にアメリカで生まれたとされています。
当時のアメリカでは女性の社会進出が進み、子育てと仕事の両立が難しくなってきた時代でもあります。
そのため、アメリカの企業では社員に対してさまざまな支援が行われるようになり、働き方に関しても多様性が徐々に生まれるようになりました。
その後、日本にワークライフバランスの考え方が浸透し始めたのは、1990年代以降になります。
当時の日本では労働環境の改善(働き方改革)により長時間労働が見直された他、女性の社会進出を手助けする”男女雇用機会均等法”などの取り組みが、積極的に行われるようになりました。
今では行政によるワークライフバランスの支援も進んでおり、大きく働き方に対する考え方が変わったといえます。
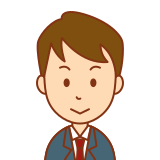
インターネットの普及により、働き方に関してはより多様性が高くなってきています。また、コロナの影響のにより政府が予見していたよりも、10年ほど早くITの浸透が進んでいるようです。
日本でワークライフバランスが求められる主な2つの理由
- 少子化に対する出産・育児支援
- 高齢化に対する働き方改革
日本でワークライフバランスが求められる理由としては、主に2つ挙げられます。
個人や企業から見たらまた別の理由が挙げられそうですが、日本という国全体で見た場合、特に重要なのは”少子高齢化“に対する対策となります。
少子化に対する出産・育児支援
夫婦共働き世帯が当たり前になってきた現代ですが、夫婦ともに働きに出てしまうと、出産や育児に対しては疎かになってしまいがちです。
そのため、日本ではワークライフバランスに関する取り組みを企業や各自治体に対して、積極的に取るように促しています。
具体的な企業側の取り組みとしては、育児休暇やフレックスタイム制などが挙げられます。
その他、出産や育児等に対する給付金制度なども、各自治体によって別途取り組んでいるところも多いです。
高齢化に対する働き方改革
日本では一番多い年代が40代後半と言われおり、他の諸外国と比較しても、かなり平均年齢が高い水準にあります。
高齢化社会といわれる現代において、高齢者の働き方に関しても改革が必要となってきています。
終身雇用制度の崩壊により、定年まで必ず雇用されるという保証は、どの企業でもできなくなってきている状況です。
その上、年金だけでは老後生活を送ることは難しいとされているため、定年退職後も働かざるを得ないという訳です。
このような現状から企業側では、退職者の”再雇用制度”を導入するなどして、働き口を増やす取り組みが背極的に行われています。
ワークライフバランスの実現による主な3つのメリット
- 仕事以外のことにも取り組みやすくなる
- 働き方が柔軟に選べるようになる
- 仕事へのモチベーションアップに繋がる
ワークライフバランスの実現により、個人が得られるメリットとしては、主に3つ挙げられます。
中でも”リモートワーク”や”在宅ワーク”が普及したことで、わざわざ出社しなくて良くなったことは、従業者にとっては大変大きな変化ではないでしょうか。
自宅で気軽に仕事に取り組める環境がある会社は、まだ日本では少数と限られてはいますが、これからより浸透していくことでしょう。
仕事以外のことにも取り組みやすくなる
ワークライフバランスが実現されることにより、より自己実現がしやすくなります。
理由としては、働き方に柔軟性が生まれたことで、プライベートな時間の確保が行いやすくなったためです。
また、家族と一緒に過ごす時間も増えたことにより、配偶者や子供たちとより良い関係性を築きやすくなったといえます。
働き方が柔軟に選べるようになる
働き方改革により各企業でリモートワークや在宅ワーク、ギグワークなどの形態が、受け入れられるようになりました。
自宅やカフェ等で気軽に仕事ができるようになったことで、仕事に対するストレスも軽減された上に、副業解禁により本業以外にもチャレンジすることが可能です。
このようなことから、自身の生活に合う働き方を気軽に選びやすくなったといえます。
仕事へのモチベーションアップに繋がる
「生活と仕事の調和」と聞くと、プライベートも仕事しなければいけないのか、と勘違いしてしまう人もいますが、それは間違いです。
生活面でも仕事に繋がるような活動を行うことで、本来の仕事に対するモチベーションのアップに繋がったり、自身のスキルや知識の向上などにも役立ちます。
何が仕事にプラスの影響を与えるかは分からないので、普段の生活でも仕事に置き換えて考える癖をつけることが大切です。
ワークライフバランスの実現に向けた企業側の主な5つの取り組み
- リモートワーク(在宅勤務)
- フレックスタイム制
- 短時間勤務制度
- 法定外福利厚生の充実
- 副業の解禁
ワークライフバランスの実現に向けた企業側の主な取り組みとしては、5つ挙げられます。
業種によっては導入が難しいところもありますが、働き方改革が行われたことで、積極的に取り入れている企業が多いのも事実です。
特にコロナ禍において、リモートワーク(在宅勤務)シフトチェンジした企業も多く、これまでのやり方から大きく変化してきています。
リモートワーク(在宅勤務)
コロナ禍における働き方の変化は、劇的とも言われるほど早い段階で行われてきました。
企業によってはまだ対応しきれていない部分もありますが、大手IT企業の多くはすでに9割程度の社員がリモートワークを実施している状態です。
ワークライフバランスとしては、リモートワークは段階的に行う計画であった企業も多かったですが、今は当たり前のように行われています。
フレックスタイム制
“フレックスタイム制”とは、出社や退社の時間を自由に選択できる制度です。
例えば朝から子供が熱を出して病院へ行かなければいけない場合、出社時間を調整してお昼から仕事に当たることもできるという訳です。
フレックスタイム制を導入している企業はまだ少数ではありますが、従業者としては自身の生活に合わせて働く時間を決定できるのは、大変大きなメリットです。
短時間勤務制度
“短時間勤務制度”とは、その名の通り労働時間を短くするための制度です。
育児・介護休業法の改正により、政府から企業に対して2009年から”短時間勤務制度”が義務付けられました。
対象者は実際に育児を行っている人に限られます。
また、具体的には1日の労働時間が8時間から6時間に短縮され、対象者は早期に退社することができるようになっています。
詳しくは厚生労働省の「短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について」をご確認ください。
法定外福利厚生の充実
“法定外福利厚生”とは、従来の法律で定められた法定福利厚生(雇用保険、健康保険、介護保険など)とは異なる、医療や健康、育児等に関するサービスを指します。
法定外福利厚生に関しては、法律では義務付けられてはいませんので、その内容に関しては企業によってさまざまです。
特に最近はワークライフバランスを意識して各企業では、健康や育児に対して力を入れているところが多いです。
家庭の負担を減らす法定外福利厚生サービスとしては、以下のようなものが挙げられます。
- ベビーシッターサービス
- 家事代行サービス
- 育児休暇(男性も取得可能)
- 子供の学習をサポートする(オンライン教材など)
それぞれ企業側が一部費用を負担したり、アウトソーシングして外部企業と提携したりして、社員が気軽にサービスを利用できるようにしているところもあります。
副業の解禁
ここ数年で副業という言葉を耳にすることが多くなってきましたが、副業が実際に解禁されたのは2018年になります。
当時は「副業元年」と呼ばれていましたが、今では多くの企業が社員に対して、副業を許可しているのが現状です。
副業に取り組むことで働き方に多様性が生まれた他、副業で学んだことを本業にも活かせるなど、相乗効果が期待できます。
現代のワークライフバランスの主な2つの問題点
- 男性の育児休暇の取得は困難である
- 管理職層の意識改善が必要である
現代のワークライフバランスの主な問題点としては、2つ挙げられます。
中でも管理職層の意識改善に関しては、どの企業でも問題になっており、80年代・90年代の人たちの理解を得るのには、まだまだ時間がかかりそうです。
男性の育児休暇の取得は困難である
ワークライフバランスが推進されてきている昨今ではありますが、男性の育児休暇の取得に関しては、悲観的な企業も多いようです。
基本的に育児休暇は女性社員に対して提供している福利厚生と認識している企業が多く、男性の育児参加に関しては、まだまだ理解が及んでいない企業が多いです。
管理職層の意識改善が必要である
長時間労働が当たり前とされてきた、80年代90年代の管理職層の人たちの意識改善に、頭を抱えている企業も少なくありません。
いくら社員がワークライフバランスに関して呼びかけても、その上の管理職層の理解が得られなければ、意味がありません。
まとめ
ワークライフバランスとは、生活と仕事の調和である、と解説してきました。
日本では働き方改革の影響もあり、最近はリモートワークを行う人たちも増えてきました。
生活面では、育児に対する企業側の取り組み方も変わってきており、以前よりも育児休暇などが取りやすくなっていると感じられます。
とはいえ、企業によってはまだまだ課題が多いところもありますので、少しつづ改善していくことが求められます。
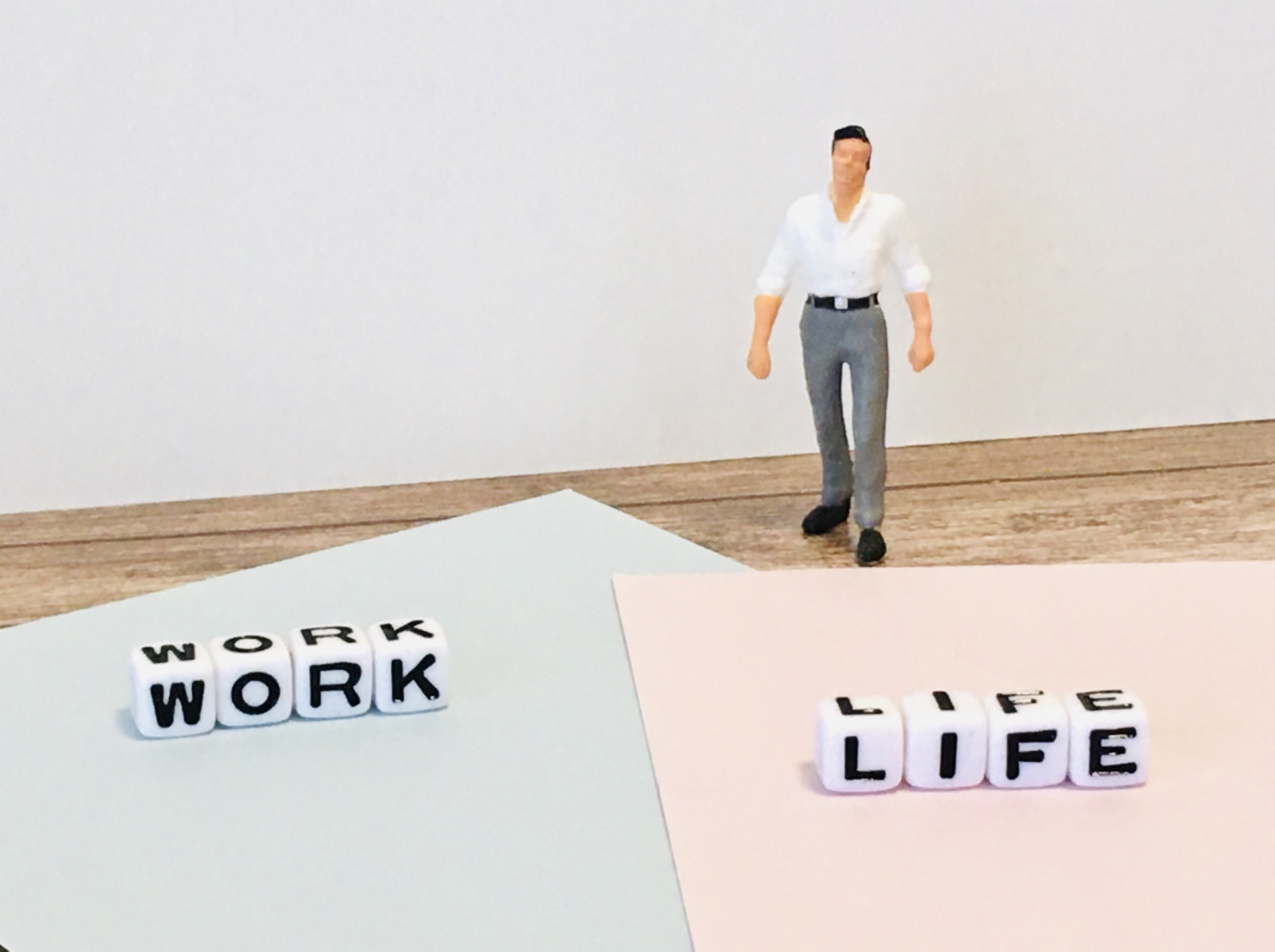


コメント