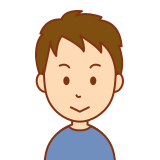
フリーランスが取引先と契約する際に交わす「業務委託契約書」に関して、詳しく知りたいです。契約締結までの流れやメリット、どちらが契約書を作成するのかなど、分かりやすく教えて下さい。
会社員の雇用契約とは異なりフリーランスは、一般的にプロジェクト単位で業務を委託する「業務委託契約」を取引先と交わします。
基本的には発注者側が契約書の作成を行い、受注者に内容確認を取った上で問題なければ、双方の同意によって契約締結となります。
発注者側から契約書の作成に関して触れられなかった場合は、受注者であるフリーランス側で契約書を作成しましょう。
業務委託契約書の作成に関しては、クラウド会計ソフトを活用すれば、容易に電子契約書が作成できます。
この記事ではフリーランスが、業務委託契約を交わす際の具体的な流れや、契約書を作成する理由に関して分かりやすく解説しています。
最後まで読んでいただくことでフリーランスの方は、不利な契約内容で締結するようなトラブルを避けることができるでしょう。
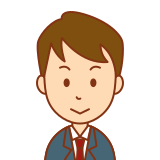
フリーランスの方は必ず契約内容を細部まで確認した上で、契約に同意するようにして下さい。
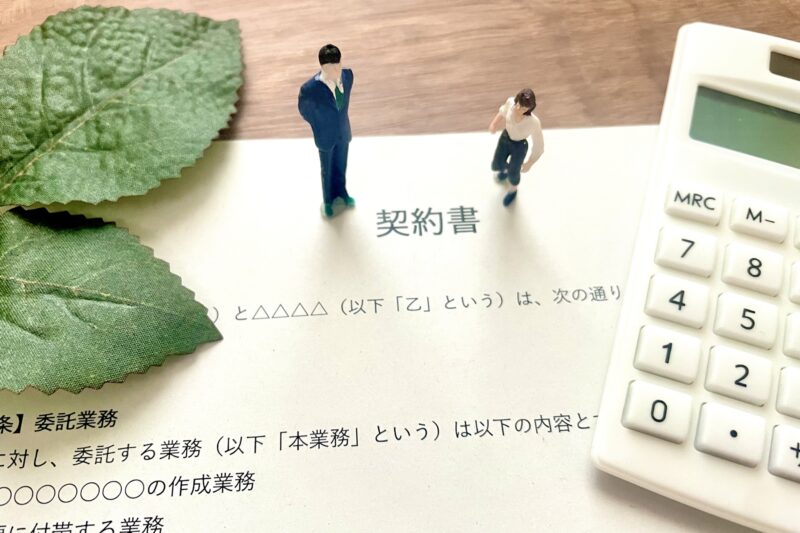
フリーランスの業務委託契約の流れ【簡単3ステップ】

フリーランスの業務委託契約の流れとしては、次の3ステップに分けられます。
- 契約内容に関して取引先と話し合う
- 業務委託契約書を作成する
- 契約内容の確認と修正を行う
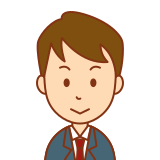
契約までの流れは実にシンプルです。
ここで重要なのは契約内容ですので、必ず不利な条件になっていないか同意する前に、細部まで確認して下さい。
契約内容に関して取引先と話し合う
フリーランスが取引先と業務委託契約を交わす前に、まずは次のような項目を双方で話し合います。
- 業務内容や業務範囲
- 実際の仕事の流れ
- 成果物の納期
- 報酬、支払い期日、支払い方法
双方ともに業務の流れに関して、ある程度把握している状態であったとしても、明確な線引きを行うように心がけましょう。
フリーランス側はこの時点で、実績や経歴などをうまく取引先にアピールし、納得のいく単価で了承してもらうことが大切です。
業務委託契約書を作成する
基本的に契約書の作成は発注者側が行い、フリーランス側に確認と同意をとってきます。
口頭だけで契約を交わす場合もあるため、万が一、発注者側が業務委託契約書の作成を行わなかった場合は、フリーランス側で作成しましょう。
その際、既存のテンプレートを活用する人が多いと思いますが、必ずご自身でも契約内容を確認して下さい。
フリーランス側で作成した契約書に不備があると、発注者側の信頼を失いかねません。
契約内容の確認と修正を行う
業務委託契約書に同意してサインする前に、最終確認を行いましょう。
業務内容や成果物の納期、報酬、支払い方法など細かい点まで、必ず目を通しておくようにして下さい。
商品の取扱説明書と同じで、読むのが面倒に感じやすい業務委託契約書ですが、不備があった際に困るのはあなた自身です。
どれだけ取引先を信頼していても、必ず契約内容には最初から最後まで目を通しましょう。
双方の合意(サイン)が得られた時点で、業務委託契約が締結となります。
フリーランスに業務委託契約が必要な理由5つ

フリーランスに業務委託契約が必要な理由としては、次の5つの項目が挙げられます。
- 業務内容を明確にするため
- 成果物の納期を明確にするため
- 報酬額や支払い方法や期限を明確にするため
- 知的財産権の帰属を明確にするため
- 秘密保持義務を明確にするため
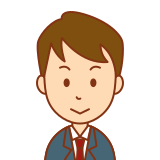
契約書は双方の権利や義務を明確にし、当事者間で起きるトラブルを未然に回避するためのものです。
業務内容を明確にするため
業務委託契約書を交わす一番の理由、といっても過言ではないのが「業務内容の明確化」です。
発注者と受注者間では度々、業務内容に関する問題でトラブルに発展するケースが多く、契約を交わすことでハッキリと業務の線引きが行えます。
フリーランス側も業務内容の線引きがハッキリとできていれば、無駄に作業を行うことなく、スムーズに作業できるでしょう。
逆に業務内容がハッキリしていないまま作業してしまうと、お互いの認識ミスにより、トラブルに発展しやすくなります。
また余談ですが、発注者が受注者であるフリーランスに対して指揮監督と捉えられるような、指示出しをしてはいけません。
フリーランス側も単なる労働力の提供ではなく、専門的な技術や知識を活用して、仕事を行う意識が大切です。
成果物の納期を明確にするため
業務委託契約書を作成する理由の一つに、成果物の納期を定める役割があります。
「フリーランスの納期遅れ」は、業界ではよくある問題であるため、発注者側はできるだけ納期遅れを防ぐために契約書に明記する訳です。
フリーランス側も契約書に同意した以上は、何がなんでも納期に送られないように成果物を納品しよう、という意識が働きます。
双方、契約書に同意し共通認識を高めることで、プロジェクトをよりスムーズに進められます。
報酬額や支払い方法や期限を明確にするため
「取引先の報酬未払い(もしくは遅延)」は、フリーランスの業界ではよくあるトラブルの一つです。
中には契約書を交わしたにも関わらず、発注者側から報酬の支払いがないケースも、過去に挙げられています。
そのような場合は、厚生労働省が認可している「フリーランス・トラブル110番」に相談を行い、法的な処置をとるべきか検討しましょう。
トラブルの際には業務委託契約書が法的な効力を発揮しますので、契約を行う際には必ず報酬額や支払い期限、支払い方法を明記して下さい。
知的財産権の帰属を明確にするため
「知的財産権の帰属」とは、簡単にいえば成果物の利用権利が、発注者と受注者のどちらにあるのか明確にするものです。
知的財産権の帰属が明記されていない場合は、利用権利は成果物を作成した受注者側にあることになります。
しかし、業務委託契約書を作成することにより、フリーランス側からみれば納品した成果物の利用権利を、取引先に譲渡する意味合いになります。
知的財産権の帰属は、発注者側から見れば極めて重要な項目であるため、案件を発注する際には必ず契約書に明記しておきましょう。
秘密保持義務を明確にするため
「秘密保持義務」とは、業務上で知り得た情報などを、外部に漏洩しないための取り決めになります。
特に発注者側が法人だった場合、秘密保持義務が厳しく設けられている場合が多く、フリーランス側は慎重に行動しなければなりません。
たとえば個人情報を扱っている大変重要な業務を任された場合、誤ってカフェなどでパソコンを開いて作業していると、情報漏洩リスクが発生します。
万が一、機密情報が外部に漏れてしまい、発注者側に損害を与えてしまうと、損害賠償請求に発展しかねません。
業務に関する内容をTwitterなどで発信する行為も、秘密保持義務に触れる可能性もあります。
フリーランス側は、軽率な行動はくれぐれも慎みましょう。
フリーランスが業務委託契約を締結するメリット・デメリット

フリーランスが業務委託契約を締結するメリットとデメリットに関しては、次のような項目が挙げられます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・業務内容が明確になる ・信頼関係の構築に役立つ ・トラブルを未然回避できる ・時間的な拘束がない ・成果によっては高い報酬が得られる | ・不利な条件で契約する恐れがある ・単発での請負になりやすい ・労働基準法が適応されない ・確定申告が必要になる ・事務手続きが面倒に感じる |
契約が完了するまでの工程が面倒に感じてしまい、中には業務委託契約を交わさずに、業務依頼を行う取引先も少なくありません。
フリーランス協会の調べによると、フリーランス全体の約4割が「口頭」での契約を行なっており、後のトラブルの原因にもなっています。
契約書はあくまでも、双方の認識を擦り合わせるために行うものであり、どれだけ信頼関係が高くてもできるだけ行うようにしましょう。
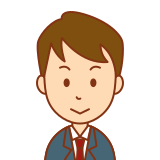
面倒に感じやすい契約書の作成に関しても、現在はマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを利用することで、簡単に作ることができます。
フリーランスが業務委託契約を行う際の注意点

フリーランスが業務委託契約を行う際に注意すべき点は、次の通りです。
- 無理に引き受けない
- 契約の種類に関して把握する
- 一方的に不利な条件でないか、足りない条項がないか確認する
フリーランスの中には仕事が欲しくて、無理に業務を引き受けようとする人もいます。
しかし、自身の力量を超える業務を無理に引き受けても、自分の首を絞めるだけです。
(今の自分には難しい業務だ…)と感じた場合は、無理に引き受けずに断る勇気を持つことも大切です。
また、単に業務委託契約といってもその種類に関しては、大きく3つに分けられます。
- 請負契約:結果に対して報酬を支払う際に結ぶ(例:大概のフリーランスが請負契約に該当する)
- 委任契約:業務の遂行自体を目的としたものであり、法律行為を行う際に結ぶ(例:税理士への税務相談など)
- 準委任契約:法律行為を行わない業務を委託する際に結ぶ(例:コンサルティングやリサーチ業務など)
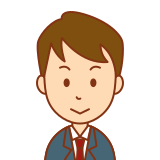
特に一方的に不利な条件を押し付けられていないか、業務委託契約書の細部まで確認することが大切です。
フリーランスの業務委託契約書における基本的な項目9つ

フリーランスの業務委託契約書に欠かせない、基本的な項目は次の通りです。
- 契約形態(請負、委任、準委任)
- 契約期間・更新日
- 業務内容(業務範囲、成果物、納期など)
- 報酬・経費の支払い
- 損害賠償・禁止事項
- 著作権・知的財産権
- 契約解除に関する取り決め
- 秘密保持義務
- 反社会勢力の排除
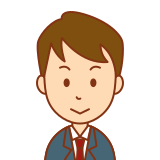
フリーランスの方は、各項目の役割をしっかりと押さえておきましょう。
契約形態(請負、委任、準委任)
業務委託契約書には、請負契約と委任契約、準委任契約の3つの種類があります。
契約形態によって報酬の支払い条件が異なるため、フリーランスの方はどの契約形態で契約書が作られているか、確認するようにしましょう。
発注者によっては契約形態を記載しない場合もありますので、その際は合意する前に双方で話し合って、どの契約形態に値するか決めておくのが無難です。
契約期間・更新日
業務委託契約には、契約期間と更新日に関する情報が記載されています。
契約期間に関しては、3ヶ月や6ヶ月、1年間など発注者によってさまざまです。
契約更新に関しては一般的に自動更新となっており、万が一、契約解除する際には契約期限の1ヶ月前に申し出るようにしましょう。
また、思わぬトラブルにより突然、契約を解除されるリスクもあります。
フリーランス側は、業務委託契約を交わしたからといって、必ずしも契約期間中の仕事が確保されているとは限りません。
業務内容(業務範囲、成果物、納期など)
業務委託契約書の中でも特に重要な業務内容の項目には、具体的な業務範囲や成果物に関する条件、納期などを明記します。
想定していない業務まで任されないようにするためにも、業務内容に関しては双方納得のいく内容を、必ず明記するように努めましょう。
万が一、業務変更を行う際には別途、双方の同意が必要である点も書いておくべきです。
合わせて受注者であるフリーランス側に、思わぬトラブルが起きた場合などの不可抗力に関する事項も、記載しておくべきでしょう。
報酬・経費の支払い
フリーランスにおける金銭トラブルは特に多いため、業務委託契約書を作成する際には、必ず報酬に関する取り決めを詳しく明記する必要があります。
報酬額はもちろんのこと、報酬の支払い期日や支払い方法なども含めて必要です。
金銭に関する認識をすり合わせておくためにも、お互いに納得のいく金額や支払い方法を、記載しておきましょう。
振り込み手数料をどちらが負担するか、なども必要事項に含まれます。
損害賠償・禁止事項
業務委託契約書には、損害賠償に該当する事項や、業務における禁止事項なども記載します。
たとえば受注者側は「指定された成果物を作成する際に、第三者に再委任してはならない」などが禁止事項に該当します。
再委任には、情報漏洩などのリスクが伴うほか、取引のコントロールが難しくなる、などのデメリットが発生するため基本的には禁止事項です。
万が一、発注者側の機密情報が第三者に漏れてしまった場合には、損害賠償請求に発展しかねません。
フリーランス側は、しっかりと禁止事項を事前に確認しておきましょう。
著作権・知的財産権
フリーランスが成果物を納品して報酬を受け取る場合は、著作権や知的財産権の譲渡に関しても、契約書に記載しなければなりません。
知的財産権とは、成果物の無断使用を防ぐためのものであり、著作権や特許権、商標権なども知的財産権に含まれます。
権利に関する認識を予め定めておかないと、後々トラブルの種になりかねませんので、契約書を作成する際には必ず明記しておきましょう。
契約解除に関する取り決め
「契約解除に関する取り決め」とは、想定されるトラブルが発生した場合、速やかに契約を解除するという趣旨を指します。
契約解除の条件としては、次のような項目がよく挙げられます。
・本契約に著しい違反が認められたとき。
・主務官庁より、営業許可停止、営業停止その他の行政処分を受け、又は信用失墜等の事由により営業が困難となったとき。
・第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他の強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞 納処分を受けたとき。
・その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
出典:マネーフォワードクラウド契約
万が一、想定外のトラブルが生じた場合は、双方話し合いの末に契約解除するかどうか、決めるのが一般的です。
秘密保持義務
業務委託契約書では、業務上で知り得た情報を外部に流出させないために、秘密保持義務に関する事項を明記します。
万が一、受注者であるフリーランス側で情報漏洩が起きたりすると、損害賠償になりかねませんので注意が必要です。
場合によっては、業務委託契約書とは別に「秘密保持契約(NDA)」を作成して、契約するケースもあります。
反社会勢力の排除
反社会勢力の排除(反社条項)とは、契約において双方が反社会的勢力でないことや、暴力的な要求を行わないことを指します。
コンプライアンスの観点から業務委託契約書にも明記することが多く、万が一、反社条項に違反した場合は、その点で契約解除となります。
双方、最低限のモラルを守って取引を行うためには、必要な項目の一つです。
フリーランスの業務委託契約書を簡単に作る方法【テンプレートあり】

業務委託契約書の作成に関しては、テンプレートを活用するのがおすすめです。
初心者が最初から作成するのは難しいため、クラウド会計ソフトなどの既存のサービスをうまく利用して、作成するのが得策です。
たとえば「マネーフォワードクラウド契約」では、電子契約書の発行ができるようになっており、双方インターネット上で合意から契約締結まで一貫して行えます。
電子契約書であれば数分で契約が完了しますので、非常に便利かつスピーディです。
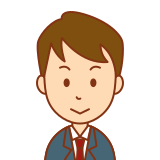
フリーランスの間では、収支管理の観点からもクラウド会計ソフトを活用するのが一般的ですので、契約に関してもオンラインで行いましょう。
フリーランスの業務委託契約に関するよくあるQ&A
フリーランスの業務委託契約に関する多くの質問や悩みの中から、特に多かった内容だけに絞って、それぞれ回答をまとめました。
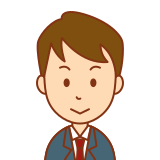
契約書に関して分からないことがある場合は、行政書士などの法律の専門家に一度、相談してみるのもおすすめです。
Q.フリーランスの業務委託契約書はどちらが作成しますか?
一般的には発注者側が契約書を作成しますが、契約書の話が出ない場合は、フリーランス側で作成しましょう。
クラウド会計ソフトに付随している、クラウド契約サービスを利用することで、ストレスなくオンライン上で契約締結まで簡単に行えます。
Q.フリーランスの契約に関するトラブルは、どこに相談したらいいですか?
フリーランスの契約や仕事上のトラブルに関しては、厚生労働省が認可している「フリーランス・トラブル110番」に相談しましょう。
無料で相談に乗ってくれる上に、相談から解決まで法律の専門家である弁護士が、ワンストップでサービスしてくれます。
Q.フリーランスの業務委託契約では、違約金などは発生しますか?
契約内容によっては、違約金が発生する可能性があります。
違約金とはいわば損害賠償に該当するため、業務委託契約書に定めてある禁止事項などを犯した際には、発注者側から損害賠償請求されるかも知れません。
双方、話し合った上で解決できれば良いですが、最悪の場合は裁判に発展するケースもあります。
Q.業務委託契約書の内容変更は、契約期間の途中からでもできますか?
双方の合意が得られれば、最初に結んだ業務委託契約書の内容変更は可能です。
たとえ契約期間の途中からでも、双方納得した上で再度「変更契約書」を発行すれば、契約の変更が行えます。
基本的に一方的な契約内容の変更はできませんので、万が一、発注者側から一方的な変更があった場合は、必ず問い合わせるようにしましょう。
Q.途中解約したい場合はどうすればいいでしょうか?
フリーランス側がやむを得ない理由により、契約期間の途中で契約解除したい場合は、発注者に一度相談しましょう。
理解のある発注者であれば、受注者であるフリーランス側の意見を汲み取ってくれるはずです。
万が一、違約金を求められた場合は、一度「フリーランス・トラブル110番」に相談してください。
まとめ
フリーランスの業務委託契約書を結ぶ際の流れに関して、わかりやすく解説しました。
- 契約内容に関して取引先と話し合う
- 業務委託契約書を作成する
- 契約内容の確認と修正を行う
契約自体は実にシンプルですが、実際に結ぶ際には必ずその内容の細部まで、確認するようにしてください。
たとえ信頼できる発注者であったとしても、一度不利な内容の契約を結んでしまうと、契約期間中はずっと不利な条件で作業することになります。
フリーランス側は必ず契約に合意する前に、内容に不備がないか確認を行い、適正な業務内容と報酬を受け取るようにしましょう。
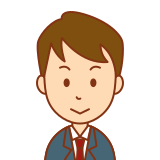
フリーランスの契約に関するトラブルは「フリーランス・トラブル110番」へご相談ください。
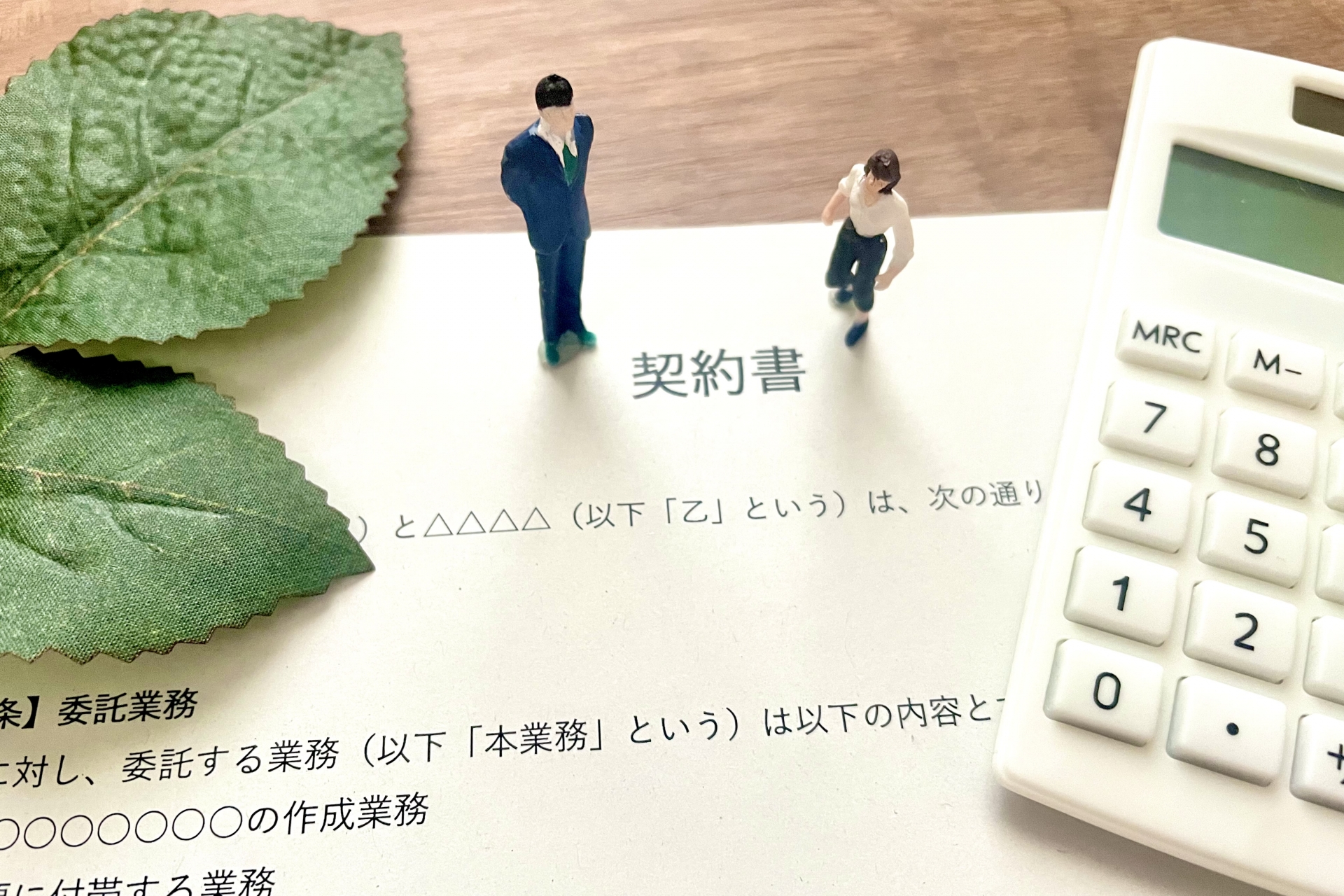


コメント