節税につながる所得控除にいくつか種類があることをご存じでしょうか。
会社員が活用できる所得控除は主に14種類あり、年末調整や確定申告をすることで適用されます。
しかし、申告を忘れたり必要書類を用意できなかったりすると、控除が受けられなくなる可能性があります。
そこで今回は、会社員が活用できる所得控除の概要を解説します。
確定申告が必要なケースも紹介しているので、確定申告をするべきか悩んでいる方も、ぜひ参考にしてみてください。
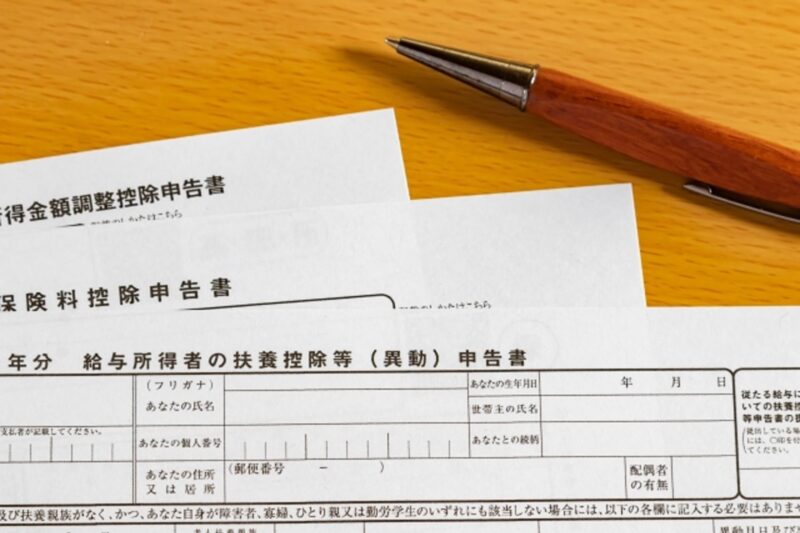
年末調整だけでは所得控除が受けられない場合がある

所得控除とは、納税者の状況に応じて所得から差し引くもので、所得税や住民税の節税効果が見込めます。
ところが、所得控除の種類によっては年末調整では適用されず、確定申告が必要な場合があります。
確定申告を忘れてしまうと、節税効果が得られなくなるため、年末調整で対応できる控除と確定申告が必要な控除を把握することが大切です。
年末調整で対応できる所得控除11選

会社員が年末調整をすることで受けられる所得控除は、主に9種類あります。
なかには、必要書類の提出が求められる控除もあるため、スムーズに申告できるように、あらかじめ対象となる所得控除を把握しておきましょう。
なお、年末調整で申告し忘れた場合は、確定申告をすることで控除が受けられます。
| 控除額 | 概要 | |
| 基礎控除 | 0〜48万円 | 所得に応じて受けられる控除 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 1〜48万円 | 納税者と配偶者の所得に応じて受けられる控除 |
| 扶養控除 | 38~63万円 | 要件を満たす扶養家族がいる場合に受けられる控除 |
| 社会保険料控除 | 支払った社会保険料の全額 | 納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の 親族の社会保険料を支払った場合に受けられる控除 |
| 生命保険料控除 | 最大12万円 | 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支 払った場合に受けられる控除 |
| 地震保険料控除 | 最大5万円 | 居住用家屋を対象とする地震保険料を支払った場合 に受けられる控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の全額 | 小規模企業共済や確定拠出年金(iDeCoなど)の掛 金を支払った場合に受けられる控除 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 夫と離婚し扶養家族がいる場合や、死別した場合に 受けられる控除 |
| ひとり親控除 | 35万円 | 婚姻をしていない、もしくは配偶者の生死が明らか でない人で子がいる場合に受けられる控除 |
| 障害者控除 | 27~75万円 | 納税者自身や同一生計の配偶者、扶養親族に一定以 上の障害がある場合に受けられる控除 |
基礎控除
基礎控除とは、特別な条件がなく、納税者のほとんどが受けられる所得控除です。
控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて以下のように定められています。
| 合計所得金額 | 控除額 |
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除・配偶者特別控除は、年収が一定額以下の配偶者がいる場合に適用されます。
年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出することで控除対象となります。
主な要件は以下の通りです。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 民法上の配偶者に該当する
- 納税者と生計を一としている
- 青色事業専従者として、その年を通して給与を受け取っていない
- 白色事業専従者でない
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、対象となる配偶者の年間所得金額の範囲です。
| 控除 | 所得 | 年収ベース |
| 配偶者控除 | 48万円以下 | 103万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 48万超133万円以下 | 201万円以下 |
控除額は、納税者本人と配偶者の年間所得金額によって以下のように決定されます。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | |||
| 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
| 配偶者控除 | 48万円以下 (※老人控除対象配偶者の場合) | 38万円 (※48万円) | 26万円 (※32万円) | 13万円 (※16万円) |
| 配偶者特別控除 | 48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
※老人控除対象配偶者は、対象の配偶者のうち70歳以上の方を指します。
扶養控除
扶養控除は、以下の要件を満たす扶養家族がいる場合に適用できます。
- 納税者本人と生計を一とする配偶者以外の親族
- 合計所得金額が48万円以下である
- 青色申事業専従者として、その年を通して給与を受け取っていない
- 白色事業専従者でない
扶養控除を受けるには、年末調整の際に勤務先へ「扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。
控除額は扶養家族の年齢によって異なります。
| 区分 | 控除額 |
| 一般の控除対象扶養親族 (16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) | 38万円 |
| 特定扶養親族 (19歳以上23歳未満) | 63万円 |
| 老人扶養親族 (70歳以上) | 同居している場合:58万円 同居していない場合:48万円 |
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族の社会保険料を支払った場合に受けられます。
控除額は支払った社会保険料の全額です。
控除対象となる代表的な社会保険料は以下の通りです。
- 健康保険料
- 国民年金保険料
- 厚生年金保険料
- 国民健康保険料
- 介護保険料
通常、給与から天引きされている社会保険料は勤務先が把握しているので、年末調整の際に対応する必要はないでしょう。
ただし、以下のようなケースは、勤務先側が把握できていないため申告が必要です。
- 会社の社会保険に未加入で、国民年金保険料や国民健康保険料を支払った
- 年度の途中で就職・転職し、国民年金保険料や国民健康保険料を払っていた期間がある
- 配偶者や親族など納税者本人以外の社会保険料を支払った
この場合は年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」と「社会保険料控除証明書」を提出しましょう。
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用されます。
控除額は、年間の支払保険料や保険の契約時期に応じて異なります。
2012年1月1日以降に契約した保険に対する控除額は以下の通りです。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| 2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円超4万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料それぞれの年間支払保険料が8万円を超える場合、生命保険料控除額は上限の12万円(4万円×3)となります。
控除対象となる場合は「給与所得者の保険料控除申告書」と保険会社から発行される証明書をセットにして勤務先に提出しましょう。
地震保険料控除
地震保険料控除は、居住用家屋を対象とする地震保険料を支払った場合に適用される所得控除です。
控除額は、年間の支払保険料の合計によって異なります。
| 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
| 5万円以下 | 支払金額の全額 |
| 5万円超 | 一律5万円 |
地震保険料控除を受けるには、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」と「地震保険料控除証明書」の提出が必要です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用されます。
対象となるのは以下の通りです。
- 小規模企業共済制度
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)
- 心身障害者扶養共済制度
控除額は、その年に支払った掛金の全額です。
年末調整の際は、支払った掛金の証明書または電子データを「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して、勤務先に提出する必要があります。
寡婦控除・ひとり親控除
寡婦控除とひとり親控除の要件や控除額は以下の通りです。
| 寡婦控除 | ひとり親控除 | |
| 結婚歴要件 | 夫と離婚もしくは死別したあと婚姻を していない人 | 婚姻をしていない、もしくは配偶者の 生死が明らかでない人 |
| 扶養要件 | 扶養家族がいる ※夫と死別した場合は、扶養家族の有 無にかかわらず適用 | 総所得金額等の合計額が48万円以下の 子がいる |
| 性別要件 | 女性のみ | 男女問わない |
| 所得要件 | 合計所得金額が500万円以下 | 合計所得金額が500万円以下 |
| 控除額 | 27万円 | 35万円 |
寡婦控除とひとり親控除を受けるには、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。
なお、2つの控除は重複して適用されません。
障害者控除
障害者控除とは、納税者自身や同一生計の配偶者、扶養親族に一定以上の障害がある場合に受けられる所得控除です。
原則、障害者手帳や障害者控除対象者認定書を持っている方が対象となります。
障害者控除で差し引かれる金額は以下の通りです。
| 区分 | 所得税控除額 |
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
障害者控除は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
確定申告が必要な所得控除3選
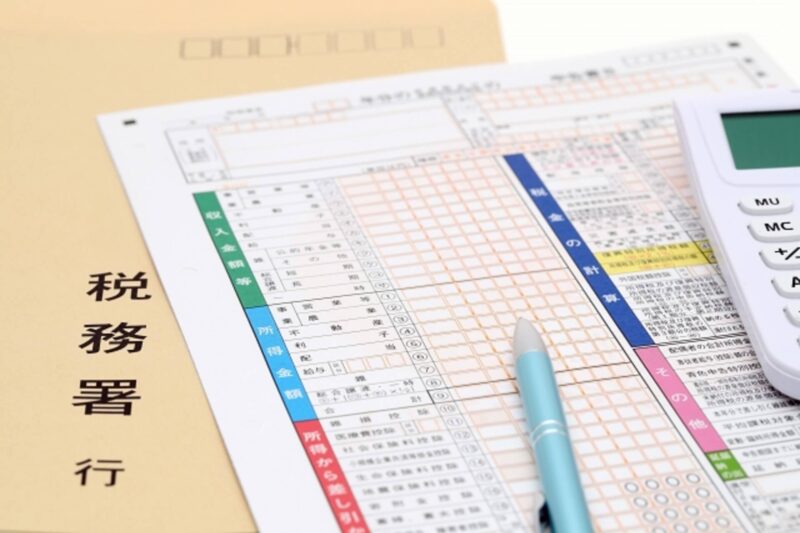
確定申告が必要な所得控除は以下の3つです。
- 医療費控除
- 寄付金控除
- 雑損控除
これらは確定申告を忘れると適用されないため、納税額が増えてしまう恐れがあります。
ただし、確定申告を忘れた場合は、還付申告をすることで納め過ぎた所得税の還付を受けられます。
還付申告ができるのは、所得を申告する年の翌年1月1日から5年間です。
医療費控除
医療費控除とは、納税者本人または生計を一とする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる控除です。
控除額(上限は200万円)は以下の計算式で算出できます。
医療費控除額 =(医療費の合計金額 ー 保険金等の補てん金額)ー 10万円(※)
※総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額の5%」で計算する。
保険金等の補てん金額は、健康保険や生命保険、出産育児一時金などで支給された金額です。
医療費控除を受けるには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があります。
なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は、選択制となっているため併用できません。
セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品を購入した際に受けられる医療費控除の特例制度です。
医療費控除は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
寄付金控除
寄付金控除は、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに「特定寄付金」を支払った場合に適用できます。
控除額は以下の計算式で算出します。
寄付金控除額=寄付金の合計額もしくは総所得金額の40%(※)-2,000円
※低い金額を採用する。
寄付金控除が受けられる身近な例は「ふるさと納税」です。
ふるさと納税の控除を受けるためには原則、確定申告が必要ですが、ワンストップ特例制度を利用すると例外的に不要となります。
ただし、医療費控除など他の控除を受けるために、確定申告する場合は注意が必要です。
ワンストップ特例制度の届出内容は、確定申告をすると無効となります。
住宅ローン控除を利用する1年目や医療費控除を受ける際は確定申告を選択しましょう。
なお、確定申告で住宅ローン控除や医療費控除を併用する際は、ふるさと納税の自己負担額が増える可能性があるため、それぞれの控除上限を確認しておくのがおすすめです。
| 確定申告 | ワンストップ特例制度 | |
| 寄付先の上限 | 上限なし | 1年間で寄付先は5自治体まで |
| 申請方法 | 税務署に寄付金受領証明書と 確定申告書を提出 | 各自治体に申請書を提出 |
| 控除対象 | 所得税と住民税 | 住民税のみ |
| 期限 | ふるさと納税をした 翌年2月16日~3月15日 | ふるさと納税をした 翌年の1月10日必着 |
雑損控除
雑損控除は災害または盗難などによって、納税者本人もしくは生計を一にする配偶者、その他の親族が保有する住宅や家財、現金などが損害を受けた場合に適用されます。
控除額は以下の2つのうち大きい方を採用します。
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-総所得金額等×10%
- 災害関連支出額-保険金等の額-5万円
災害関連支出額は、火災後の片付けや解体費用などが挙げられます。
損失額が大きくその年の所得金額から控除しきれなかった場合は、毎年確定申告をすることで翌年以降3年間に渡って繰り越しが可能です。
確定申告の際は、申告書の雑損控除に関する事項を記載し、罹災(りさい)証明書や災害記録、災害に関連した支出の領収書などを添付します。
住宅の修理後は、罹災証明書の発行ができなくなるため、被災した状況を証明できる写真を必ず撮影しておきましょう。
住宅ローン控除を利用する1年目は確定申告が必要

医療費控除や寄付金控除のほかに、住宅ローン控除を受ける際も確定申告が必要です。
住宅ローン控除は所得控除ではなく、納税額から直接差し引かれる「税額控除」の一つです。
会社員は1年目に確定申告をすれば、その後は基本的に年末調整で税額控除が受けられます。
住宅ローン控除は大きな減税につながるケースが多いので、忘れずに申告しましょう。
対象となる所得控除がある場合は忘れずに申告しよう
所得控除を利用すると、納税額が減ったり、還付金が受け取れたりする節税効果が得られます。
会社員が利用できる所得控除のなかには、年末調整で受けられる控除と、確定申告が必要な控除があります。
利用したい控除がどちらの方法で適用されるのかを把握し、忘れずに申告しましょう。
申告方法に不安がある方は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してみるのがおすすめです。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
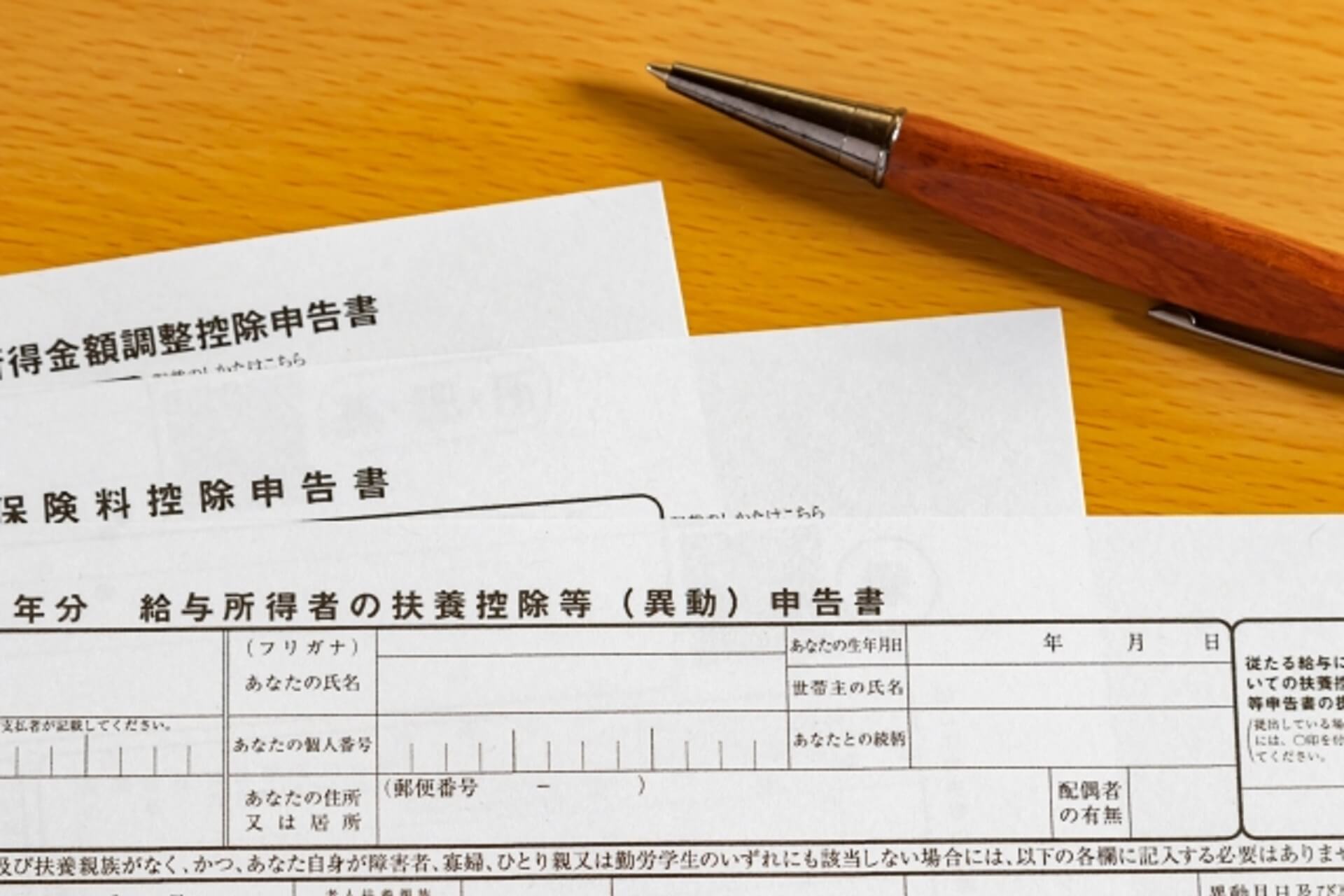


コメント